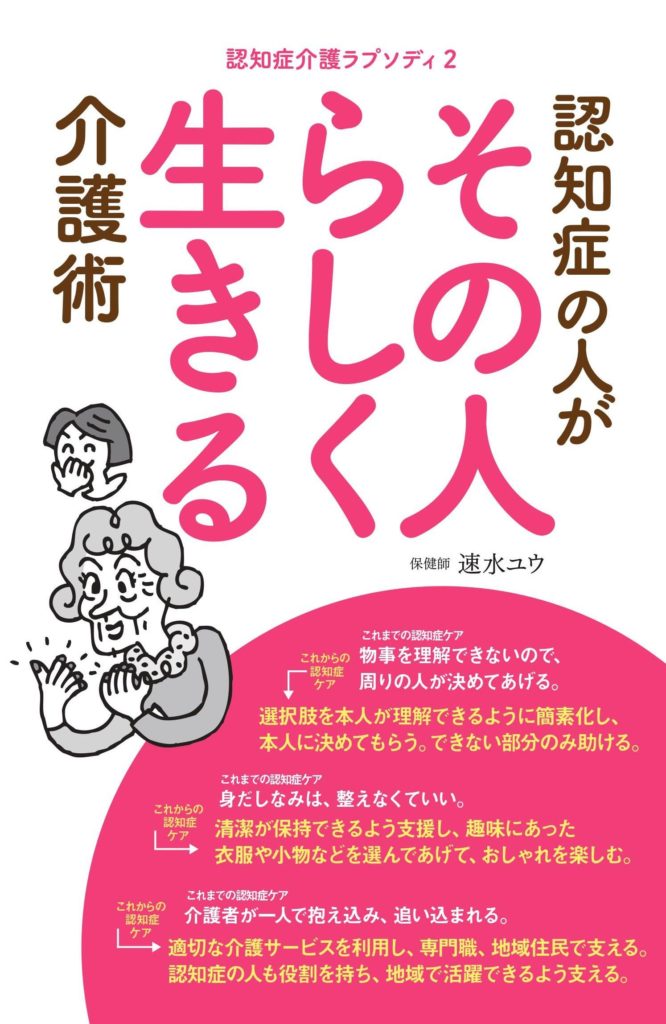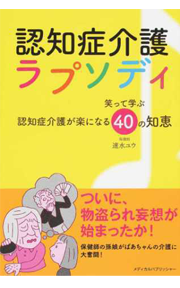お雛様を出しました
お雛様を婆ちゃんの退院の日に出しました。何でそんな忙しい日にかというと、その日しか私と母の予定がただ合わなかったからです。私のために、亡くなった祖父(認知症介護ラプソディのヒロイン婆ちゃんの夫)が買ってくれた7段飾りです。母には戦後で貧しくて、買ってあげられなかったので、その分私にはいいのを買ってあげたいと祖父は思って買ってくれたそうです。婆ちゃんと違ってじいちゃんは、自分本位ではなくとても面倒見のいい優しい爺ちゃんだったんですよ。今は私の2歳の娘のために出しています。母の子どもの頃は、金持ちの薬剤師さんの家くらいにしか、近所でお雛様を持っている人がいなかったとか。それを聞いて、お雛様って裕福な家の人しか楽しめなかったのか、そんな疑問が起こりました。

お雛様の起源は縄文時代までさかのぼる
お雛様の起源をたどると縄文時代の土偶や古墳時代の埴輪にさかのぼるそうです。意外ですよね~、土偶や埴輪の顔は雛人形の顔とは程遠いですから。平安時代の人形は、災いや厄を払う意味があったそうです。徐々に身代わりになってもらい、川に流す風習がすたれていき子どもの誕生を祝うものになっていったそうです。室町時代には雛祭りは、白酒や餅を食べる楽しい行事だったそうです。江戸時代に入り、雛祭りはますます盛んになり、幼児のお祓いの意味はうすれ、女の子が飾って遊ぶ行事になったそうです。今と同じ風習なのは、江戸時代からなんですね。今では、女の子が誕生したら、両親または祖父母が健やかな成長と幸福を願い贈るものになっています。

貧富の差によるお雛さまの祝い方の違い
うちの母が子供のころ、戦後は周りには、雛人形を持っているお友達が一人しかいなかった。お金持ちのお家だけだった。そこに皆見に行っていたようです。うちの元上司(教授)が芦屋のあたりのいいお家から、古い雛人形を回想ルーム(学生に勉強させるために、昔の家具などが置かれている大学のある一室)で展示するようにもらってきたことがありました。その件からもいいお家だけだったのかなと疑問が残ります。歴史的に宮中で楽しんでいたようなものなのか、町娘も楽しむようなものだったのか、機会があれば調べてみたいです。女性のダイバーシティ(多様性)について今は言われますが、それは、きっと昔からあったはず。お雛様を通して歴史を反芻するのも素敵な楽しみ方かもしれません。
季節の行事を楽しむことは認知症の人にも子どもにもよい
季節の行事は、幼稚園や保育園でも高齢者のデイサービスなどでも大事にされていますね。子どもにいいことと認知症の人にいいことはよく重なります。認知症の人には、季節の行事が過去を思い出すことにつながり、認知症の人を心理的に安定させたり、認知症の進行予防を促したりもします。これを専門的には回想法といいます。高齢者も子供も世代を超えて、季節の行事を楽しむのは、世代間交流や文化の継承も生まれるのですばらしいことですね。うちは、お雛様を2階に出してしまったので、婆ちゃんが上がって見れないかもしれませんが、お雛ケーキ、ひなあられ、ひし餅などを婆ちゃんとともに楽しみたいと思っています。