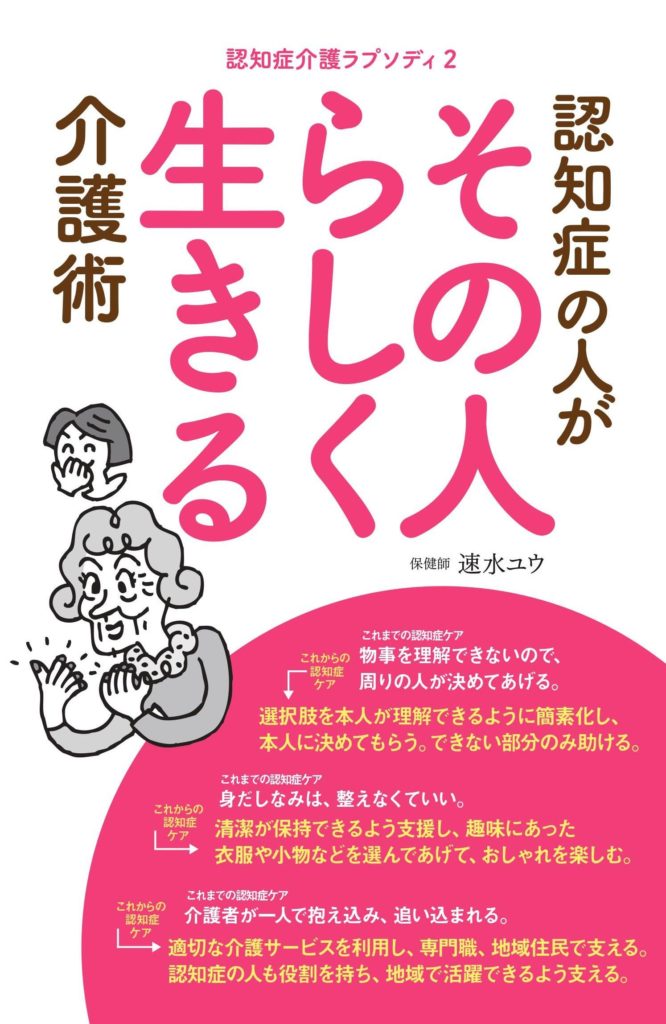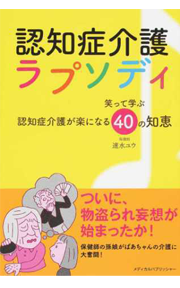Photo by rawpixel.com on Pexels.com
いつの間にか3割負担開始
介護保険の利用料3割負担が2018年8月、つまり今月から開始していたのをご存じですか?いつも改正の実施は何だか見逃しがちになりそうな8月開始が多いですね。知らない間にどんどん変わっていく介護保険ですね。介護保険制度開始から関わっている私は行く末を見守り続けたいと思っています。
今回の改正はいったいどういうことなのか?介護保険料ではなく利用料、つまり介護サービスの自己負担料の改正なんです。皆一斉に3割負担になるわけではありません。現役世代並みの所得がある介護保険の介護サービスを利用している高齢者のみです。
具体的には、合計所得金額が220万以上あり、単身世帯なら年金収入とその他所得金額が340万円以上の人、2人以上世帯なら年金とその他所得金額が463万円以上の人になります
3割負担になる人は上位3%の人々で約12万人にあたります。国の規模からすると、非常に裕福な層の方々にあたるかと思います。
うちの婆ちゃんは、フルタイムの正職員調理師で課税でしたが、認知症のため、身体障害者手帳(精神障害者福祉手帳)をとってからは非課税扱いなのも功を奏してか、1割負担のままです。
介護保険は改悪ばかりなのか?
介護保険の介護サービス利用料の自己負担額はもともと一律1割でした。はじめは、所得に関係なく1割だったんですよ。それこそ不自然だったなと思います。
高額介護サービスの制度があるにしても・・。
介護サービスの自己負担料を裕福な層が多く負担することに関しては私は賛成です。
しかしながら、介護保険の要支援の人々の通所介護や訪問介護を介護保険から外していく、そして要介護1,2の人々もはずしていくという意向ですよね。こちらは、どんどん対象者をはずしていったら、そもそも介護保険って何だったんだろうか?という制度破綻につながると思います。
高齢者の人口が増えるのはわかっていたのに、なぜ、ここまで介護費用が高くなり、制度がたちゆかなくなることを予測できなかったのか?
いつも、そう思ってしまいます。
これは、私の憶測ですが、介護保険が始まる当初はまだまだ人々が介護サービスに慣れていなかった。まだまだ嫁の介護というのも残っていて、サービスに踏み切れない人々がいた。
しかしながら嫁の介護の役割というのも薄れていき、人々は予想以上に介護サービスに慣れていった。人口増加の割合分だけでは予測できない部分があったのではないか。そう考えています。
介護保険が始まった当初も要支援の人は介護保険の対象者とては諸外国に比べて軽すぎるのではないかとは思っていました。でも、そのやり方で開始した以上、責任ある対応を国はしないといけないですね。