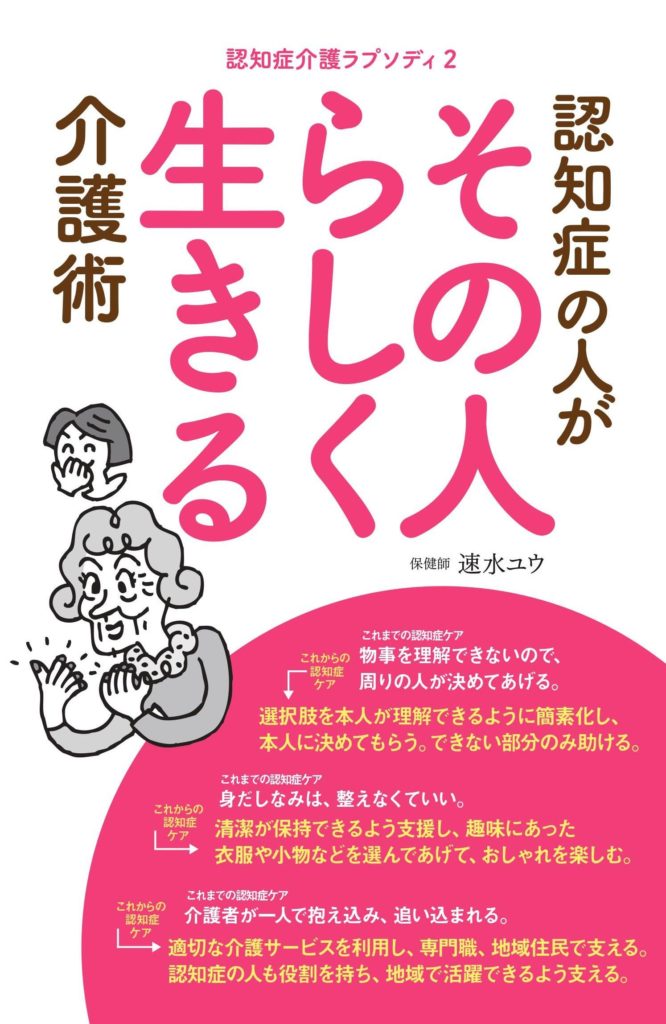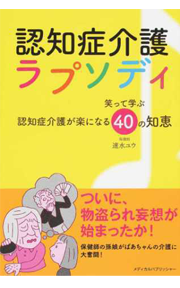アメリカにいる頃にその方法を知った
私が「企画のたまごやさん」を知ったのは、アメリカにいたときなんです。アメリカで私は女性学を学んでいたのですが、その学部の卒業した先輩にあたる人が「アメリカで女性学を学ぶような女たち」という本を出したいからと執筆を頼まれたんです。正直、売れそうな本ではないなと思いました。私のように女性学を学びたいと思い、アメリカに渡る人はやはりまれですから…。その人が「企画のたまごやさん」に出してみようと思うと言っていて、無名の人が商業出版できるそんな方法があるんだと知ったんです。

企画のたまごやさんは編集者が独立
昔は、原稿を一社、一社持ちこまないといけなかった。無名の人が原稿を持ち込んで、相手にしてもらうなんて、やはり、至難の業。しかも、気が遠くなるような作業です。ところが、企画のたまごやさんができてからは、そういう方法をとらなくても、効率的に原稿を持ち込めるようになりました。たまごやさんに原稿の一部を送れば、担当の人が決まり、多くの出版社に一斉配信してくれるというしくみなんです。はじめは、たまごやさんというオフィスに多くの社員がいるというようなイメージをしていたんですが、編集者の人と関わっている間にそうではないということがわかってきました。編集者の人はそれぞれ独立した編集者さんなんです。たまごやさんという会社に所属する編集者さんたちではないんですね。つまり、たまごやさんと提携している独立している編集者さんが、手挙げ式で担当者として関わってくださるんです。私の場合はいくつかの認知症関連の本を手掛けてらっしゃるベテラン編集者さんが手挙げしてくださいました。

4社のオファーがきた
たまごやさんの編集者さんが、私の企画を上手に宣伝文句をつけて多くの出版社に一斉配信してくださいました。私の本は、ストーリーで学ぶ実用書なんですが、はじめは「婆ちゃんはマジシャン」というタイトルにするか、実用書らしく「認知症介護を学ぶ40の知恵」というようなものにするか悩ましいところだったんです。編集者さんは、小説だとほとんど出版社からのひきがないから、実用書らしい仮タイトルにすることをアドバイスしてくださり、それに従いました。配信すると、ダイヤモンド社さんを含む3社からのオファーがすぐに来て、その時は編集者さんからも、感触はすごくいいと言われました。オファーが来ると、原稿を全部お見せすることになります。全部お見せした後のダイヤモンド社さんの返答は、「原稿の内容はいいんですが、ブログで1位とか、何か数字の実績がありますか?」と言われました。私の場合は、ランキングに入るどころか、ブログを始めてもいませんでした。「数字がないと、会議にすらかけられないんですよ」と。そうやって、3社のオファーはぬか喜びとなってしまったのです。落胆していたところ、遅れて新しい出版社からのオファーが来ました。それが今お世話になっているメディカルパブリッシャーさんです。自分としては聞いたことのない出版社だったので、企画のたまごやさんの紹介だからきちんとした出版社だとわかっていても、まだ信用していいのかなという気持ちでした。ところが、結果的にはとても誠実な出版社だったんですよ。わざわざ大阪まで会いに来て出版社や出版の流れについて、説明してくださるし、新聞広告も読売新聞、毎日新聞、地方新聞等に広告を新刊じゃなくなっても何度も出してくださるんです。

印税の30%はたまごやさんの取り分に
企画のたまごやさんは、ボランティアというわけでは、ありません。印税の30%はたまごやさんに支払うことになります。たまごやさんが扱うのはすべて商業出版になります。自費出版は含みません。うちの出版社の場合は、私にその分を支払ったら、手間になるだろうからと、出版社から直接たまごやさんの編集者さんに支払ってくださっています。この取り分が多い、少ないは賛否両論ですが、無名の人にきちんとした出版社を探してくれるのだから、それ相応の報酬だと思っています。

大きい有名な出版社だとよいとは限らない
書店の方から教えてもらったことですが、小さい出版社の方が本を大事にしてくれるそうです。大きい出版社は大きい分社員の数が多いですし、多くの本を同時に出版し、従業員のお給料を支払うためにも多くの新刊をどんどん出していかないといけないわけです。だから、1冊の本にそんなにかまっていられないんです。短期間でサクサクと出していかないといけないので、思い入れもそれ相当になることが考えられます。本の新刊の期間は3か月と言われています。大きい出版社ほど新刊の期間を過ぎると、作家にあまりかまってくれなくなるようです。もちろん、爆発的に売れる場合は違うと思いますが…。大きい出版社だと置いてもらえる書店や本の数が多くなるという利点がありますが、芸能人の本のようにワゴンいっぱいにというわけにはなかなかいかないかなと思います。うちの出版社の場合は、本を作るのに7か月もかけてくださいました。たまごやさんの編集者さんには、「まさか、こんなにかかるとは思いませんでした」と言われました。メディカルパブリッシャーさんの編集者さんは、大手出身ですが、「1つの本にじっくりこれぐらいは、時間をかけたい」とおっしゃっていました。たまごやさんの編集者さんには、「メディカルパブリッシャーさんの編集者さんは、私がこれまで会った最も熱心な方かもしれません」と言われました。それを聞くと、私は本当にラッキーだったなと思いました。
商業出版を意識して
「うちの認知症の婆ちゃんのことを面白おかしく書いたら、誰かの役に立つんじゃないか」初めは、そんな感じの思いつきでした。しかし、自費出版は出したくない。老年看護の教員でしたが、認知症のことの第一人者というわけでもない私です。じゃあ、そんな私が、どうしたら、商業出版できるだろう。商業出版をするために思いついたのは、「独自性」と「実用性」でした。たとえば、有名人が介護した本であれば、その介護の様子が単調な本であっても読みたいと思う人が多くいるでしょうね。何月何日、こんなことがありましたというような単調な本であっても。しかしながら、無名の人が介護した本が単調だったら、多分誰も興味をそそられないですよね。だから、コメディタッチにしたんです。実際、ユニークでいじわる婆さんみたいな婆ちゃんですしね。無名の人のコメディ小説でも出版社からのひきは、少ないだろうということも予想できました。だから、ストーリーで学ぶ実用書にしたんです。ただの小説では出版社からのひきがないけども、ストーリーで学ぶ実用書なら、4つの出版社からの反応があったわけです。

顔の見える関係がいい
メールが当たり前の現代では、自分の本を編集してくれる人と顔を合わすこともなく、本が作られることもあります。それは、なんだか寂しいですね。顔を見て、話したことがあるかないかで、メールを読んだときの印象も違ってくるなと思います。何でもメールやライン等のSNSになりがちな現代ですが、アナログの本を作る時は、特にアナログな関係を大事にしたいなと思っています。

商業出版と自費出版の違い
誰でもわかることですが、商業出版と自費出版ではこちら側がお金を出すかどうかが違います。お金の違い以外の決定的な違いは、売ろうと頑張ってくれるかどうかです。自費出版の場合は、自費を出している分、すでに出版社が儲かっているので、売ろうとしてはくれません。もちろん、形だけの新聞広告が1回等はあります。宣伝するためというよりも、自費出版でお金を出している作家を納得させるためという感じです。昔と違って、新聞広告もそれほど今は高額ではありません。そして、1回の新聞広告では、それほどの効果は期待できません。例えば、阿川佐和子さんの本が出版されると、新聞に同じ広告が何度も載りますよね。何度も何度も載って、「あぁ、この本出たんだ」と読者は認識します。ところが、買いたいなと思っても忙しくて忘れてしまったりもしますよね。また、広告が出て、「そうそう、この本買いたいと思ってたんだ。今度こそ買おう」となると思います。1回だけの広告か、何度もある広告かって、読みたい読者にあたる確率だけでなく、同じ人へのアプローチも継続的になるんですね。自費出版でもまれに、爆発的に売れる場合もあります。しかしながら、本当にまれです。そのまれな場合を期待する形で、無名の作家に自費出版を勧める場合もあるかと思いますが、やはり、めったに起こることではないのは事実であると思います。

自費出版は自費出版で役割がある
私は、自費出版を否定したいわけではなく、自費出版にも役割があると思っています。商業出版は商業ですから、確実に売れそうな本しか出したくないわけです。つまり、それはマジョリティ(大多数)向けということ、専門書でなり限り、数の少ないマイノリティに届く本はなかなか作ろうとしないわけです。それはそれで哀しいことですね。多くの人に届きそうな、ざっくりとした本しか作らないという風にもとらえられます。自費出版の本は、マイノリティを対象とした本も多数見られます。よく目にするのが、障害者の親御さんが出版した本です。健常者に比べると障害者の人の数はかなり少ないですよね。商業出版では、なかなか出せるはずのものではありません。しかしながら、その親御さんのメッセージがつまった本は別の同じような境遇の親御さんにどれほど励みになることか。マイノリティの親同士だとなかなか出会えないこともあるかと思います。自費出版の本には商業出版では、埋められない別の役割があるのだと私は思っています。
本を誰かが手に取って読んでくれるのって素敵なこと
自費出版にしても、商業出版にしても、遠くの誰かが本を手に取って読んでくれるのって素敵なことですよね。ブログと違って本は、内容をしっかり検閲され、誤字はもちろんのこと、文章もどんどん研ぎ澄まされたものになっていきます。そんな澄み切ったイメージを私は本に抱いています。おもしろいことに、同じ本を読んでも、印象に残るところって人によって全然違うんですよね。1巻の「認知症介護ラプソディ」の本からは、読者の皆様がそれぞれに自分に必要なメッセージを受け取ってくださった。そんな風に感じています。

2巻はもっとメッセージ性を高めたい
1巻は、頭に思い浮かぶままに書いたような感じなのですが、2巻はもっと意識してメッセージ性を高めたいと思っています。アメリカでアメリカ史を学んでわかったことですが、共産主義が迫害されていた時代は、メッセージ性の高い本がいくらか出ていたんです。アメリカ史の授業でそんな本をたくさん読まされました。直接的な表現ができないから、ストーリーを通して暗に社会が良い風に変わっていくよう表現していたんですね。ストーリーを通した社会活動って何だか素敵だと思いませんか。私の場合は、認知症の人や家族が生きやすくなることにつながるメッセージを届けていきたいですね。でも、コメディなんですけどね。2巻も、泣いたり笑ったりと忙しい本になりそうです。最後は自分の本の話をしてしまいましたね。まだまだ私も駆け出しですが、これから出版する方に私の経験が参考になればと思って書いてみました。